子の引き渡しについて
離婚の話し合いをしている途中や、あるいは離婚して夫婦の一方が子どもを引き取った場合でも、相手が勝手に子どもを連れ去るケースがたびたび見受けられます。
そんなときでも、力づくで子どもを連れ戻すことは認められません。法的手続きを踏んで、正当な方法で子の引き渡しを受ける必要があります。
子の引き渡しとは
子の引き渡しとは、正当な理由なく連れ去られた子どもを取り戻すための法的手続きのことです。
離婚協議中の夫婦や、離婚した元夫婦の間では、どちらが子どもを育てるかで激しい争いとなることがよくあります。なかには、子どもと離れたくない一心で勝手に子どもを連れ去るような親もいます。
- 離婚協議中、子どもを連れて出ていかれた
- 子どもを連れて別居していたが、学校から帰宅中の子どもを連れ去れれた
- 離婚後の面会交流中に子どもを連れ去れれた
このようなケースが典型例です。
勝手に子どもを連れ戻す行為は違法なので、たとえ相手が先に子どもを連れ去ったとしても、実力行使で子どもを連れ戻すようなことを考えてはいけません。正当に子どもを連れ戻す方法として、以下のような法的手続きが用意されています。
子の引き渡しを求める法的手続き
連れ去られた子の引き渡しを求める法的手続きとして、「子の引き渡し調停・審判」といいうものがあります。ただし、とるべき手続きの流れは夫婦が離婚する前の場合と離婚後の場合とで少し違います。
(1)離婚前
離婚する前は、子どもを連れ去った相手にも親権がありますので、そのままでは子の引き渡しを求めることはできません。そのため、「子の引き渡し調停・審判」を申し立てる前に、または同時に「子の監護者の指定の調停・審判」を申し立てる必要があります。
監護者の指定とは、離婚が成立するまでの間、子どもを養育すべき親を暫定的に裁判所に決めてもらうことです。
引き渡しを求める側が監護者に指定された場合、引き続き子の引き渡しについて調停または審判を行うことになります。
なお、「子の監護者の指定」も「子の引き渡し」も、調停をせずいきなり審判を申し立てることが可能です。子の引き渡しが問題となるようなケースでは、夫婦の話し合いで解決できる可能性が低いため、最初から「子の監護者の指定の審判」と「子の引き渡し審判」を申し立てるケースもあります。
(2)離婚後
離婚後、親権者でない親が子どもを連れ去り、親権者が子の引き渡しを求める場合には、「子の引き渡し調停・審判」のみを申し立てれば足ります。
他方、子どもが親権者に虐待されているようなケースでは、親権者でない親が子の引き渡しを求めることもあるでしょう。このような場合には、「子の引き渡し調停・審判」を申し立てる前に、または同時に「親権者変更調停・審判」を申し立てる必要があります。
親権者変更が認められた場合、引き続き子の引き渡しについて調停または審判を行うことになります。
なお、親権者変更についても、調停をせずいきなり審判を申し立てることが可能です。
審判前の保全処分が重要
子の監護者指定や子の引き渡しの審判は、離婚調停や離婚裁判より早く結果が出ますが、それでもある程度の期間がかかります。結果が出ても、相手が不服申し立てをすると高等裁判所で再審理されるため、審判が確定するまでに長期間を要することがあります。
その間、相手が子どもを養育していると、「継続性の原則」により離婚時には相手が親権者に指定される可能性が高まってしまいます。
このようなリスクを避けるために有効な手続きが、「審判前の保全処分」というものです。
審判前の保全処分とは、本案である子の引き渡しの審判結果を待たずに、家庭裁判所が暫定的な措置として、相手方に対して子どもを引き渡すように命じる処分のことです。
離婚後でも、そのままにしておくと子どもの身に危険が及ぶような緊急のおそれがある場合には、審判前の保全処分が有効です。
審判前の保全処分の申し立ては、子の引き渡し調停・審判の申し立てと同時でも構いませんが、前に行うこともできます。早めに子どもを取り戻すためには、早急に審判前の保全処分のみを申し立てるのもよいでしょう。
監護者指定・子の引き渡しの判断基準
監護者の指定や子の引き渡しは、審判を申し立てたからといって必ずしも認められるわけではありません。
認められるかどうかの判断基準は、離婚の際に親権者を決める判断基準とほぼ同じで、次のような要素が重視されます。
- 今までどちらが主に子育てをしてきたか
- 母親の方が父親より有利になりやすい
- 兄弟姉妹はできる限り引き離さない方がよい
- 子どもがどちらとの生活を望んでいるか(特に15歳以上の場合)
- 親の経済・健康の状態が健全か
- 子育てに協力してくれる人がいるか
その他にも、相手が暴力を振るって子どもを連れ去ったり、嫌がる子どもを無理やり連れ去った場合のように、連れ去り行為の違法性が高い場合には、子の引き渡しが認められやすくなります。
逆に、連れ去り後に相手が子どもと円満に暮らしており、問題なく養育しているような場合には、子の引き渡しが認められない理由のひとつとなる可能性もあります。
子どもを引き渡してもらう方法
審判や審判前の保全処分で子の引き渡しが命じられた場合には、子どもを連れ戻すことが可能となります。しかし、相手が引き渡しを拒むこともあります。このような場合は、家庭裁判所から相手方に対して子どもを引き渡すように説得や勧告をしてもらうことができます(履行勧告)。
それでも引き渡しを拒まれる場合は、強制執行の申し立てが可能です。具体的には、一定期間内に子どもを引き渡さなければ金銭の支払いを命じるという間接強制や、裁判所の執行官が相手方の自宅等で強制的に子どもの引き渡しを求める直接強制などの方法があります。
ただし、強制的な手段をとると子どもに精神的な負担をかけるおそれがあるため、なるべく任意的な手段を優先するようにしましょう。
子の引き渡しは弁護士に相談を
子の引き渡しに関する法的手続きは早急に行うことが肝要ですが、的確に進めるためには専門的な知識を要します。
また、相手が監護者に指定されてしまうと、離婚裁判でも相手が親権者に指定されてしまうことがほとんどです。
早急に子どもを取り戻したい場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士を間に入れると、話し合いで早期に解決できる場合もありますし、法的手続きが必要な場合でも迅速に進めてもらえます。
当事務所でも子の引き渡しに関するご相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。
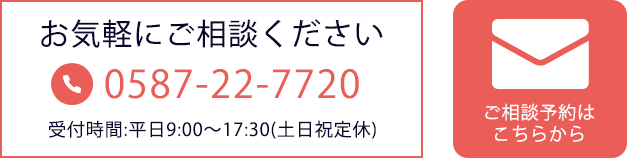
 0587-22-7720
0587-22-7720
 親による子どもの連れ去りに対処するには?引き渡し調停・保全処分のポイント
親による子どもの連れ去りに対処するには?引き渡し調停・保全処分のポイント  離婚の知識
離婚の知識





